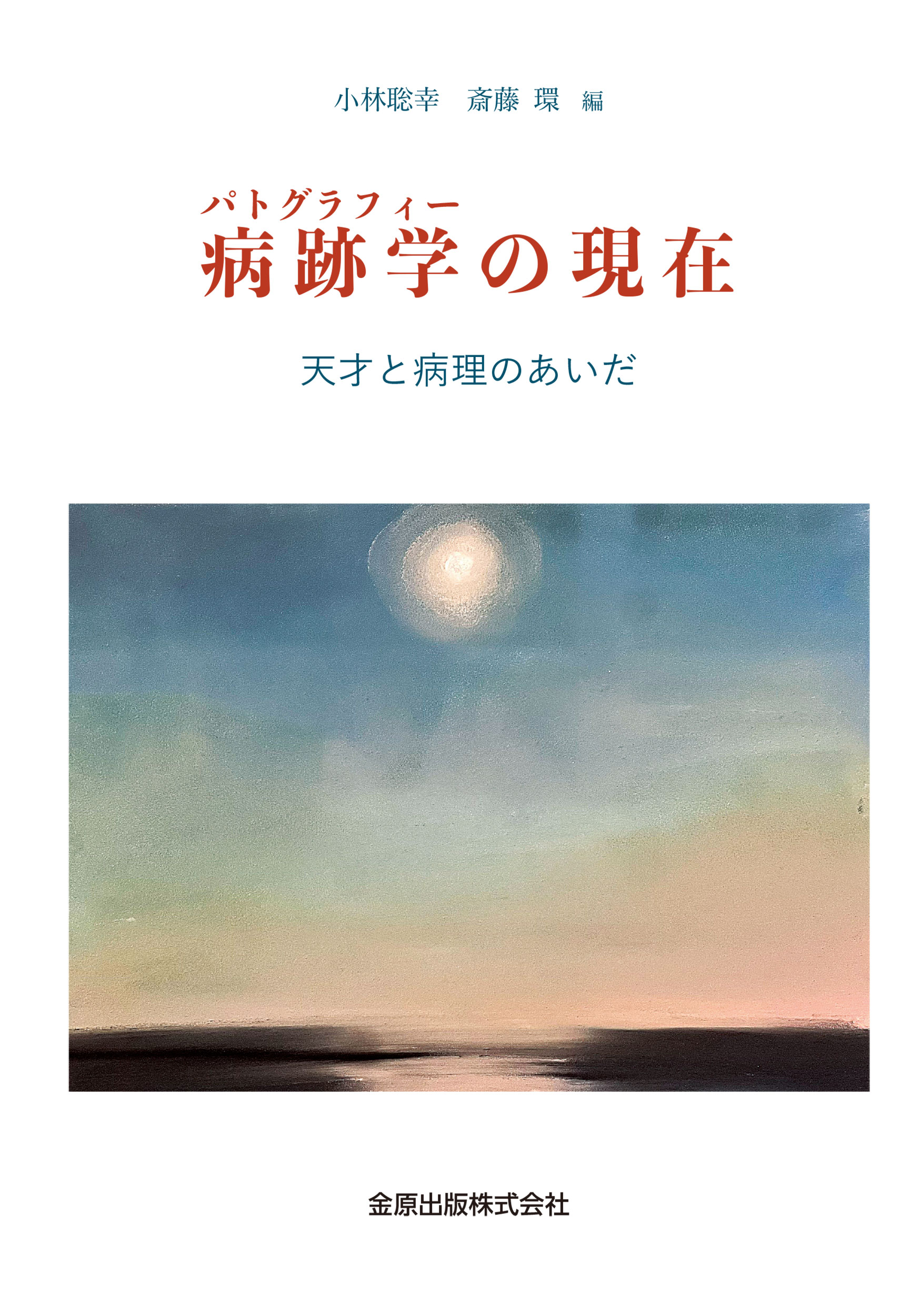Copyright© KANEHARA & Co., LTD. All Rights Reserved.
病跡学(パトグラフィー)の現在 天才と病理のあいだ
パトグラフィー20年の精華をここに。病跡学への唯一のてびき書

病跡学(パトグラフィー)とは歴史的に傑出した人物を精神医学の観点から系統的に研究をしようとするものである。本書は最近約20 年のパトグラフィー論文を選りすぐり、単行本未収載作を集約し、加えてパトグラフィーへの手引きを掲載した、かつてない企画である。これからパトグラフィーを読んでみたいという方、またパトグラフィー研究に従事してみたいという方、さらには海千山千の研究者に対しても好個となる一冊。
第1部 パトグラフィーへようこそ
・病跡学(パトグラフィー)の現状と課題 (田中伸一郎)
・「 」と病跡学 (佐藤晋爾)
・中井久夫におけるトラウマと「文体の獲得」 (松本卓也)
・パトグラフィーの書き方 (小林聡幸)
第2部 疾患と創造の相即相入
・エドヴァルド・ムンクが描出した統合失調症性の両価性 (角田京子)
・幼年期の踏査――アドルフ・ヴェルフリの妄想的自叙伝について―― (上尾真道)
・セザンヌのタンペラマン――不肖の父の肖像―― (内海 健)
・ヒルデガルト・フォン・ビンゲンと側頭葉てんかんにおける神秘体験――異言は何故真理を語るのか、また、ヒステリーは異言を語りうるか―― (兼本浩祐、大島智宏)
・サド侯爵の拘禁反応 (小畠秀吾)
・フィリップ・K・ディックと穴だらけの世界 (小林聡幸)
第3部 自閉症スペクトラムの創造性
・スタンリー・キューブリック論 または私は如何にして彼のドリー撮影と自閉症児の電車好きが関係していると悟ったか (小林 陵)
・伊藤若冲――創造性の地下水脈としての自閉スペクトラム特性―― (華園 力)
・グレン・グールドの病跡、リズム論への寄与、演奏史上の位置 (津田 均)
第4部 サルトグラフィーの試み
・坂口恭平――健康生成としての創造―― (斎藤 環)
・色川武大の『狂人日記』――絶望を描いた希望の書 (齋藤慎之介)
・からだでしかないじぶん――癌患者としての伊藤計劃と創造性 (風野春樹)
・庵野秀明のサルトグラフィー (斎藤 環)
第5部 病跡学のダイバーシティ
・死と音楽――宮城道雄と内田百間の創造性の接点にあるものを巡って―― (牧瀬英幹)
・安部公房の「夢の論理」と「論理の夢」 (番場 寛)
・作家・森茉莉における少年愛の幻想と「父」 (村田智子)
・車寅次郎の虎気質について (杉林 稔)
・システム的制作のプロセス――デヴィッド・リンチ (河本英夫)
・ウォーホルとポップ哲学――病跡学的再考―― (花村誠一)
・付録1:ブックガイド パトグラフィー必読書 23冊 (斎藤 環)
・付録2:『日本病跡学雑誌』人名目録(第51号〜第100号) (小林聡幸)
・病跡学(パトグラフィー)の現状と課題 (田中伸一郎)
・「 」と病跡学 (佐藤晋爾)
・中井久夫におけるトラウマと「文体の獲得」 (松本卓也)
・パトグラフィーの書き方 (小林聡幸)
第2部 疾患と創造の相即相入
・エドヴァルド・ムンクが描出した統合失調症性の両価性 (角田京子)
・幼年期の踏査――アドルフ・ヴェルフリの妄想的自叙伝について―― (上尾真道)
・セザンヌのタンペラマン――不肖の父の肖像―― (内海 健)
・ヒルデガルト・フォン・ビンゲンと側頭葉てんかんにおける神秘体験――異言は何故真理を語るのか、また、ヒステリーは異言を語りうるか―― (兼本浩祐、大島智宏)
・サド侯爵の拘禁反応 (小畠秀吾)
・フィリップ・K・ディックと穴だらけの世界 (小林聡幸)
第3部 自閉症スペクトラムの創造性
・スタンリー・キューブリック論 または私は如何にして彼のドリー撮影と自閉症児の電車好きが関係していると悟ったか (小林 陵)
・伊藤若冲――創造性の地下水脈としての自閉スペクトラム特性―― (華園 力)
・グレン・グールドの病跡、リズム論への寄与、演奏史上の位置 (津田 均)
第4部 サルトグラフィーの試み
・坂口恭平――健康生成としての創造―― (斎藤 環)
・色川武大の『狂人日記』――絶望を描いた希望の書 (齋藤慎之介)
・からだでしかないじぶん――癌患者としての伊藤計劃と創造性 (風野春樹)
・庵野秀明のサルトグラフィー (斎藤 環)
第5部 病跡学のダイバーシティ
・死と音楽――宮城道雄と内田百間の創造性の接点にあるものを巡って―― (牧瀬英幹)
・安部公房の「夢の論理」と「論理の夢」 (番場 寛)
・作家・森茉莉における少年愛の幻想と「父」 (村田智子)
・車寅次郎の虎気質について (杉林 稔)
・システム的制作のプロセス――デヴィッド・リンチ (河本英夫)
・ウォーホルとポップ哲学――病跡学的再考―― (花村誠一)
・付録1:ブックガイド パトグラフィー必読書 23冊 (斎藤 環)
・付録2:『日本病跡学雑誌』人名目録(第51号〜第100号) (小林聡幸)
ハイデガーと並び20世紀最大の哲学者と評されるウィトゲンシュタインは、『哲学宗教日記』において、この世の中で生きる上での自分の苦悩がいかに自身の思索活動と密接に結びついているのかについて実に雄弁に語っており、教えられるところが多い。本書が主眼とする、文学、絵画、音楽などの芸術、また哲学、宗教、物理学、医学などの思想・学問等における人々の卓越した創造活動と、「遺伝子―言語複合体」としての人間の精神(・心身)のゆらぎ・失調との関係の在り方を記述し、考察するパトグラフィー(ないし病跡学)と銘打たれている学の導入にふさわしい内容なので、いくつか断章を抜粋したい。
「私は大部分の人間よりもむき出しの魂を持っている。私の天才とはいわば、そこにあるのだ」(1932年1月28日)。
自分が天才であるという確信を表明しているこの言葉は、世界を揺るがした著作『論理哲学論考』を完成させた頃に書かれている。その判断は、ウィトゲンシュタインにあって誇大的な妄想的な思い込みではおよそなく、根拠があるものであることは、平均的な人との比較をして語る次の言葉から納得できるだろう。
「私の思考装置は飛びぬけて複雑で繊細な造りであり、そのため普通より敏感なものだと思う」。「もっと粗い仕組みなら妨害しないような多くのことが、この装置の働きを妨害し、活動できなくする。小さな塵が精巧な器具を止めても、もっと大造りの器具には影響を与えないように」(1930年10月16日)。
「飛びぬけて複雑で繊細な造り」をし「普通より敏感」などという言葉は、ウィトゲンシュタインが極めつきの高い知性と極めつきの繊細な感性の持ち主であることを明解に語る。それゆえに、他人の存在や話、周囲の物音に非常に敏感になること、またそのため自分の思考装置が働かなくなる。つまり、人の多い雑踏などでは疲れやすく集中力が下がる。逆に、人里離れたところだと才能を発揮できる。これは、ウィトゲンシュタインがノルウェーの人里離れた村にときどき行き、思索を深めたことを思い起こせば、合点がいくところである。
自分の才能を表現するのに使用された「思考装置」「器具」といった表現は、言語を機械とみる考え方に通じる。各人に固有な言語器械を想定できるはずで、ウィトゲンシュタインの言語器械はこの上なく犀利につくられている。
ウィトゲンシュタインは「他の人」と違って、自分には「精神」の次元が生きるのにふさわしい場であることも洞察している。
「私がより精神的な次元に赴く場合、その次元においては自分で人間であることができる。そこでは私は正しいのである」。
「これに対して、他の人間たちはそれほど精神的ではない次元においても人間であることができるのだ」。
「まさに私は建物のその階に彼らのような権利をもっていないのだ。そして彼らの次元においては、そして彼らの次元においては、正当にも自分に劣等感を感じるのである」(1931年5月6日)。
ここでウィトゲンシュタインは、普通の健常な人々の住処となる「世俗的な共同社会」と、高次な哲学的思索や宗教的思索の場となる「精神の世界」を峻別し、普通の人は世俗的な共同社会において「人間となることができる」のとは対照的に、自身は精神の世界において初めて「人間となることができる」と述べる。世俗的共同社会では異邦人で生きづらく、劣等感をもたざるをない。ここにいるとき、疎隔感や異邦人である感覚も生じる。それゆえ、日常の世界においては自分は異常であるという病識も備わっている。「自分の思考(哲学的思考)に対する喜びとは、私自身の奇妙な生に対する喜びである。これは生きる喜びなのか」(1931年10月24日)という言葉からわかるように、精神の次元に赴くと、生きる喜びが体験される。
この言葉は正常と異常の区別を相対化する視点を提示しており、精神医学や心理学にとっても貴重である。
「くだらないことほどに私が恐れているものはなく、くだらないことほど私が無条件に避けたいと思うものはない」。
「私は並はずれて臆病であり、戦場で臆病者が振る舞うように人生で振る舞っている」(1931年11月2日)。
ウィトゲンシュタインが最も苦手とする「くだらないこと」の端的な例は、井戸端会議といった日常生活の中で人々が親しげに笑いながら話す、他愛のないお喋りだろう。こうした俗世間の交流が怖いため、ひどく臆病になり、自分に閉じこもってしまうことも認める。
ウィトゲンシュタインは世俗的共同社会でたくましい健常人とともに生きる誘惑さえ拒絶し、精神の次元での孤高の生を選択する。要するに、彼は極めつきの精巧な言語機械ゆえに生来、俗世間に生理的といってよい違和感をもち、むしろ穢れのない精神世界に親和性をもつ。
現代の精神医学を席巻する、発達障害をめぐる「言語ゲーム」(ウィトゲンシュタイン)からすると、ウィトゲンシュタインをアスペルガー症候群、ないし自閉スペクトラム症(ASD)と診る見解が主流になっている。診断指標(ギルバーグ)に準拠して吟味すると、(1)社会的な障碍、(2)狭い興味関心、(3)決まった手順の繰り返し(常同性)、(4)話し方と言語の問題、(5)非言語的コミュニケーションの問題、(6)運動機能のぎこちなさなどの指標は、すべて満たす。しかし、この診断指標の大きな問題は、対象とする事例の創造性に関わる長所は全く見ようとせず、世俗社会に生きる平均的な人物像をモデルにしてすべてマイナス面しかみない点である。
ウィトゲンシュタインの側にたっていえば、「むき出しの魂を持ち」「飛びぬけて複雑で繊細な造りをして」、要するに極めつきの並はずれた高い知性及び極めつきの並はずれて繊細な感性をそなえている者からすると、人間のさまざまな意志・欲望と虚偽が交錯している世俗社会はこの上ない猥雑な代物で、通俗的な社会関係を築くことは非常に難しい。他方「むき出しの魂を持つ」者は、高次の精神世界に惹かれ、邪悪な世俗社会から逃れ、「デモニッシュなもの」に駆動されて、自分の全精力をただ1つの焦点に集中させる。「狭い興味関心」は、また「決まった手順の繰り返し(常同性)」も高い創造性に一心不乱に傾注する者にとり平凡な日常生活と引き換えのもので、当然の結果だろう。
ウィトゲンシュタインは4歳まで自発的な発語がなく、話し始めてからは長い期間吃音が続いたという。それにもかかわらず、彼の言語能力は人並外れたものであることは誰しも認めるところである。彼が呈した発語の遅れ、また吃音の出現は、乳幼児期からすでに「むき出しの魂を持ち」「飛びぬけて複雑で繊細な造りをして」、極めつきの高い知性・感性をもった状態にあったことを想定するなら、納得できる現象だと考える。その傍証として、ウィトゲンシュタインの幼年時代の写真を持ち出すことができるのではないだろうか。大きく見開いた目をして、しっかりした眼差しで前方をしっかり見据え、実に聡明な表情をしている。ただならない緊張感をたたえているようで、極めつきの高い知性・感性を生来備えていることをうかがわせる。
事例ウィトゲンシュタインに対する以上のような了解の仕方から、パトグラフィーの学の方法論の一端が伺えることと思う。敢えて一言でいえば、パトグラフィーは、個人の創造性の生成過程について、その人のパーソナリ特性ないし、精神(・心身)の揺らぎとの関連から了解性を高めることに寄与をする学といえるのではないか。そこでは、創作者と作品に敬意を表しつつ、正常・異常の2分割を棚上げして「狂い」を内に取り込んだ豊かな人間知がもたらされることが意味深いと考える。
パトグラフィーの領域は非常に広く、学際的で、問題枠の射程も大きい。従来パトグラフィーは、本書でいえばセザンヌ、ウォーホールなど、名前をよく知られた傑出人が多く扱われるが、パトグラフィーは勿論、日常を生きるどこにでもいる無名の人びとによるささやかな創造性を考察の対象にする布置もそなえている。
実際、精神科外来や病棟で出会う患者さんの創作活動もパトグラフィーの射程に入る。このようにして、パトグラフィーは精神科臨床あるいは心理臨床の発展に大きな寄与をすることだろう。現代の精神医学は薬物療法を重視するあまり、作品創造による自己治癒の営為を含む広義の精神療法に対する視点が乏しい。この点で、パトグラフィーの領域の重要性が増していると考える。
高齢化社会に入りパトグラフィーの関心領域は、拡大している。近年、高齢になっても俳句を作り続け、それが生きがいになって元気に暮らしている人、あるいは重篤ながんを患い、緩和ケア期にもかかわらず、創作活動を続け、これが大きな支えになっている人など、創造活動により、高い生活の質が保たれ、精神科的問題が回避されている事例は少なくなくない。そうした事例は、まさしくパトグラフィーの対象になる。
創造活動が逆境を跳ね返すレジリエンスの働きをしているという視点は、医学一般において重要で、その意味では、パトグラフィーは医学における治療のなかに採択されてしかるべき重要な学であることを付け加えておきたい。
自治医科大学名誉教授 日本病跡学会元理事長
加藤 敏
「私は大部分の人間よりもむき出しの魂を持っている。私の天才とはいわば、そこにあるのだ」(1932年1月28日)。
自分が天才であるという確信を表明しているこの言葉は、世界を揺るがした著作『論理哲学論考』を完成させた頃に書かれている。その判断は、ウィトゲンシュタインにあって誇大的な妄想的な思い込みではおよそなく、根拠があるものであることは、平均的な人との比較をして語る次の言葉から納得できるだろう。
「私の思考装置は飛びぬけて複雑で繊細な造りであり、そのため普通より敏感なものだと思う」。「もっと粗い仕組みなら妨害しないような多くのことが、この装置の働きを妨害し、活動できなくする。小さな塵が精巧な器具を止めても、もっと大造りの器具には影響を与えないように」(1930年10月16日)。
「飛びぬけて複雑で繊細な造り」をし「普通より敏感」などという言葉は、ウィトゲンシュタインが極めつきの高い知性と極めつきの繊細な感性の持ち主であることを明解に語る。それゆえに、他人の存在や話、周囲の物音に非常に敏感になること、またそのため自分の思考装置が働かなくなる。つまり、人の多い雑踏などでは疲れやすく集中力が下がる。逆に、人里離れたところだと才能を発揮できる。これは、ウィトゲンシュタインがノルウェーの人里離れた村にときどき行き、思索を深めたことを思い起こせば、合点がいくところである。
自分の才能を表現するのに使用された「思考装置」「器具」といった表現は、言語を機械とみる考え方に通じる。各人に固有な言語器械を想定できるはずで、ウィトゲンシュタインの言語器械はこの上なく犀利につくられている。
ウィトゲンシュタインは「他の人」と違って、自分には「精神」の次元が生きるのにふさわしい場であることも洞察している。
「私がより精神的な次元に赴く場合、その次元においては自分で人間であることができる。そこでは私は正しいのである」。
「これに対して、他の人間たちはそれほど精神的ではない次元においても人間であることができるのだ」。
「まさに私は建物のその階に彼らのような権利をもっていないのだ。そして彼らの次元においては、そして彼らの次元においては、正当にも自分に劣等感を感じるのである」(1931年5月6日)。
ここでウィトゲンシュタインは、普通の健常な人々の住処となる「世俗的な共同社会」と、高次な哲学的思索や宗教的思索の場となる「精神の世界」を峻別し、普通の人は世俗的な共同社会において「人間となることができる」のとは対照的に、自身は精神の世界において初めて「人間となることができる」と述べる。世俗的共同社会では異邦人で生きづらく、劣等感をもたざるをない。ここにいるとき、疎隔感や異邦人である感覚も生じる。それゆえ、日常の世界においては自分は異常であるという病識も備わっている。「自分の思考(哲学的思考)に対する喜びとは、私自身の奇妙な生に対する喜びである。これは生きる喜びなのか」(1931年10月24日)という言葉からわかるように、精神の次元に赴くと、生きる喜びが体験される。
この言葉は正常と異常の区別を相対化する視点を提示しており、精神医学や心理学にとっても貴重である。
「くだらないことほどに私が恐れているものはなく、くだらないことほど私が無条件に避けたいと思うものはない」。
「私は並はずれて臆病であり、戦場で臆病者が振る舞うように人生で振る舞っている」(1931年11月2日)。
ウィトゲンシュタインが最も苦手とする「くだらないこと」の端的な例は、井戸端会議といった日常生活の中で人々が親しげに笑いながら話す、他愛のないお喋りだろう。こうした俗世間の交流が怖いため、ひどく臆病になり、自分に閉じこもってしまうことも認める。
ウィトゲンシュタインは世俗的共同社会でたくましい健常人とともに生きる誘惑さえ拒絶し、精神の次元での孤高の生を選択する。要するに、彼は極めつきの精巧な言語機械ゆえに生来、俗世間に生理的といってよい違和感をもち、むしろ穢れのない精神世界に親和性をもつ。
現代の精神医学を席巻する、発達障害をめぐる「言語ゲーム」(ウィトゲンシュタイン)からすると、ウィトゲンシュタインをアスペルガー症候群、ないし自閉スペクトラム症(ASD)と診る見解が主流になっている。診断指標(ギルバーグ)に準拠して吟味すると、(1)社会的な障碍、(2)狭い興味関心、(3)決まった手順の繰り返し(常同性)、(4)話し方と言語の問題、(5)非言語的コミュニケーションの問題、(6)運動機能のぎこちなさなどの指標は、すべて満たす。しかし、この診断指標の大きな問題は、対象とする事例の創造性に関わる長所は全く見ようとせず、世俗社会に生きる平均的な人物像をモデルにしてすべてマイナス面しかみない点である。
ウィトゲンシュタインの側にたっていえば、「むき出しの魂を持ち」「飛びぬけて複雑で繊細な造りをして」、要するに極めつきの並はずれた高い知性及び極めつきの並はずれて繊細な感性をそなえている者からすると、人間のさまざまな意志・欲望と虚偽が交錯している世俗社会はこの上ない猥雑な代物で、通俗的な社会関係を築くことは非常に難しい。他方「むき出しの魂を持つ」者は、高次の精神世界に惹かれ、邪悪な世俗社会から逃れ、「デモニッシュなもの」に駆動されて、自分の全精力をただ1つの焦点に集中させる。「狭い興味関心」は、また「決まった手順の繰り返し(常同性)」も高い創造性に一心不乱に傾注する者にとり平凡な日常生活と引き換えのもので、当然の結果だろう。
ウィトゲンシュタインは4歳まで自発的な発語がなく、話し始めてからは長い期間吃音が続いたという。それにもかかわらず、彼の言語能力は人並外れたものであることは誰しも認めるところである。彼が呈した発語の遅れ、また吃音の出現は、乳幼児期からすでに「むき出しの魂を持ち」「飛びぬけて複雑で繊細な造りをして」、極めつきの高い知性・感性をもった状態にあったことを想定するなら、納得できる現象だと考える。その傍証として、ウィトゲンシュタインの幼年時代の写真を持ち出すことができるのではないだろうか。大きく見開いた目をして、しっかりした眼差しで前方をしっかり見据え、実に聡明な表情をしている。ただならない緊張感をたたえているようで、極めつきの高い知性・感性を生来備えていることをうかがわせる。
事例ウィトゲンシュタインに対する以上のような了解の仕方から、パトグラフィーの学の方法論の一端が伺えることと思う。敢えて一言でいえば、パトグラフィーは、個人の創造性の生成過程について、その人のパーソナリ特性ないし、精神(・心身)の揺らぎとの関連から了解性を高めることに寄与をする学といえるのではないか。そこでは、創作者と作品に敬意を表しつつ、正常・異常の2分割を棚上げして「狂い」を内に取り込んだ豊かな人間知がもたらされることが意味深いと考える。
パトグラフィーの領域は非常に広く、学際的で、問題枠の射程も大きい。従来パトグラフィーは、本書でいえばセザンヌ、ウォーホールなど、名前をよく知られた傑出人が多く扱われるが、パトグラフィーは勿論、日常を生きるどこにでもいる無名の人びとによるささやかな創造性を考察の対象にする布置もそなえている。
実際、精神科外来や病棟で出会う患者さんの創作活動もパトグラフィーの射程に入る。このようにして、パトグラフィーは精神科臨床あるいは心理臨床の発展に大きな寄与をすることだろう。現代の精神医学は薬物療法を重視するあまり、作品創造による自己治癒の営為を含む広義の精神療法に対する視点が乏しい。この点で、パトグラフィーの領域の重要性が増していると考える。
高齢化社会に入りパトグラフィーの関心領域は、拡大している。近年、高齢になっても俳句を作り続け、それが生きがいになって元気に暮らしている人、あるいは重篤ながんを患い、緩和ケア期にもかかわらず、創作活動を続け、これが大きな支えになっている人など、創造活動により、高い生活の質が保たれ、精神科的問題が回避されている事例は少なくなくない。そうした事例は、まさしくパトグラフィーの対象になる。
創造活動が逆境を跳ね返すレジリエンスの働きをしているという視点は、医学一般において重要で、その意味では、パトグラフィーは医学における治療のなかに採択されてしかるべき重要な学であることを付け加えておきたい。
自治医科大学名誉教授 日本病跡学会元理事長
加藤 敏
- 医書.jpで購入される方は
こちらから (外部サイトに移動します) - m3.comで購入される方は
こちらから (外部サイトに移動します)
今、パトグラフィー(病跡学)はどこに向かおうとしているのだろうか。
と、病跡学の泰斗のひとり福島章が述べたのは世紀の変わり目である。四半世紀を経て、今われわれはどこまで来たのだろうか。
引用したのは福島章・中谷陽二編『パトグラフィーへの招待』(金剛出版、2000)「はしがき」の冒頭である。19世紀末、ロンブローゾによって口火を切られたパトグラフィーは一時的に燃えあがったものの、あとはくすぶっているだけなのに、日本では専門の学会――日本病跡学会――をもち、定期的に充実した専門誌が発行されていると綴られる。そして病跡学とは何か、どのような方法と発想を獲得すべきか、どのような意義を持つか問われていると続けられている。
『パトグラフィーへの招待』が上梓されたとき、福島をはじめとした斯界の論者の個人論集はあっても、このような入門書的なものはなく、わくわくして手に取ったものだ。もっとも、最初の章にパトグラフィーの紹介的な文章がいくつかあるほか、「第一線で活躍する著者たちに、それぞれの生涯の研究の軌跡や主題や方法などを書いていただくという趣旨で編集した」というだけに、内容的には必ずしも入門に留まらない。
病跡学に携わるものとして、そのような趣旨の本がもっとあってもいいと思うのだが、同書もすでに絶版である。考えてみれば、当時の福島や、同書に遺稿が掲載された宮本忠雄の年齢に自分たちも近づいてきているのであって、「パトグラフィーへの再招待」をするのはわれわれの仕事なのだと思うに至った。
当初はパトグラフィー入門のような本を構想したが、パトグラフィーには決まった方法論も発想法もあるわけではないし、そもそもが極めて学際的なものであって、むしろ一様には捉えがたいところこそが魅力である。研究者には、精神科医や心理師だけではなく、内科医や看護師、人文科学研究者などもいる。だいたい、本稿においても、病跡学とパトグラフィーと、その名称も揺れている上に、エピ−パトグラフィーだ、サルトグラフィーだと新たな術語も登場する。本書の第1部はややひねったパトグラフィー入門である。病跡学展望の最新のもの、病跡学が「重宝するもの」であることを説く論考、そして「書き方」。そこに中井久夫論を加えたのは、中井が病跡学の先達であること、その中井の「書くこと」を論じた病跡学者(パトグラーフ)の病跡であること、さらにわれわれが病跡学を「書くこと」に関わっているという三重のひねりがある。
第2部以降は「入門」というより「成果」である。『招待』以降に『日本病跡学雑誌』をはじめとする医学雑誌に掲載された病跡学論文の中から印象的なものを選りすぐった「病跡学の現在」をお示しする。単行本収録作は避けているので、雑誌のバックナンバーを除けば本書でしか読めないものである。
何ごとにつけ定義した途端に定義からあぶれるのが常であるが、病跡学とは、「精神的に傑出した歴史的人物の精神医学的伝記やその系統的研究」(宮本)、「精神医学や心理学の知識をつかって、天才の個性と創造性を研究しようというもの」(福島)といった規定は病跡学の核を押さえてはいるだろう。だが、前掲書で中谷は、古来からの天才研究に連なる、その病跡学の核のまわりに、精神病患者の制作物の症状学的特徴への関心や、精神分析的な手法を用いた文学作品の解釈などやや異なった関心や方法が交錯してきたと述べている。そしていまや交錯するものは質も量もふえてきているのである。
第2部には、天才の創造性と――精神疾患から気質まで幅はあるが――その病理との関係を精神医学・心理学の文脈で論ずるという比較的オーソドックスな病跡学論文を集めた。が、それは「比較的」であって、例えばヴェルフリは病理と創造を扱うとともに精神病患者の制作物への関心の文脈にもある。
近年の動向として、神経発達症(発達障害)への関心の強まりがあるが、自閉スペクトラム症、あるいはもう少し広げて自閉症スペクトラムの病跡学を第3部に収めた。神経学的特性と表現とを単純に結びつけるだけでいいのかとか、統合失調気質(分裂気質)や中心気質との相違など深めるべき論点は多々あるが、病跡学の向かう道のひとつである。
第4部はサルトグラフィーに充てた。病理が創造性に影響を与えるばかりでなく、創造性が病理を緩和したり、いい影響を与えるという視点は昔からなかったわけではないが、より積極的に創造性と健康生成を論じていこうというのはもう一人の編者である斎藤環が打ち出したコンセプトである。また、身体疾患の病跡学に属する論考もここにある。
以上のように分類してみたものの、それはいささか強引だと思わざるを得ないほど、個々の論文の方向性は一様なものではないのだが、さらに第5部においてはラベルを貼りきれず、収拾のつかない様々な傾向をご覧いただく。「死」、「夢」、登場人物の病跡学、比較病跡学、精神分析的作品論、システム論……
パトグラフィーはどこまで来たのか、そしてさらにどこに向かうのか。
本書によって、パトグラフィーという領域があることを知らなかった方にその面白さを伝えたい。そして自分もこのような研究に参画したいという方をお招きしたい。
ようこそパトグラフィーの世界へ。
小林 聡幸
と、病跡学の泰斗のひとり福島章が述べたのは世紀の変わり目である。四半世紀を経て、今われわれはどこまで来たのだろうか。
引用したのは福島章・中谷陽二編『パトグラフィーへの招待』(金剛出版、2000)「はしがき」の冒頭である。19世紀末、ロンブローゾによって口火を切られたパトグラフィーは一時的に燃えあがったものの、あとはくすぶっているだけなのに、日本では専門の学会――日本病跡学会――をもち、定期的に充実した専門誌が発行されていると綴られる。そして病跡学とは何か、どのような方法と発想を獲得すべきか、どのような意義を持つか問われていると続けられている。
『パトグラフィーへの招待』が上梓されたとき、福島をはじめとした斯界の論者の個人論集はあっても、このような入門書的なものはなく、わくわくして手に取ったものだ。もっとも、最初の章にパトグラフィーの紹介的な文章がいくつかあるほか、「第一線で活躍する著者たちに、それぞれの生涯の研究の軌跡や主題や方法などを書いていただくという趣旨で編集した」というだけに、内容的には必ずしも入門に留まらない。
病跡学に携わるものとして、そのような趣旨の本がもっとあってもいいと思うのだが、同書もすでに絶版である。考えてみれば、当時の福島や、同書に遺稿が掲載された宮本忠雄の年齢に自分たちも近づいてきているのであって、「パトグラフィーへの再招待」をするのはわれわれの仕事なのだと思うに至った。
当初はパトグラフィー入門のような本を構想したが、パトグラフィーには決まった方法論も発想法もあるわけではないし、そもそもが極めて学際的なものであって、むしろ一様には捉えがたいところこそが魅力である。研究者には、精神科医や心理師だけではなく、内科医や看護師、人文科学研究者などもいる。だいたい、本稿においても、病跡学とパトグラフィーと、その名称も揺れている上に、エピ−パトグラフィーだ、サルトグラフィーだと新たな術語も登場する。本書の第1部はややひねったパトグラフィー入門である。病跡学展望の最新のもの、病跡学が「重宝するもの」であることを説く論考、そして「書き方」。そこに中井久夫論を加えたのは、中井が病跡学の先達であること、その中井の「書くこと」を論じた病跡学者(パトグラーフ)の病跡であること、さらにわれわれが病跡学を「書くこと」に関わっているという三重のひねりがある。
第2部以降は「入門」というより「成果」である。『招待』以降に『日本病跡学雑誌』をはじめとする医学雑誌に掲載された病跡学論文の中から印象的なものを選りすぐった「病跡学の現在」をお示しする。単行本収録作は避けているので、雑誌のバックナンバーを除けば本書でしか読めないものである。
何ごとにつけ定義した途端に定義からあぶれるのが常であるが、病跡学とは、「精神的に傑出した歴史的人物の精神医学的伝記やその系統的研究」(宮本)、「精神医学や心理学の知識をつかって、天才の個性と創造性を研究しようというもの」(福島)といった規定は病跡学の核を押さえてはいるだろう。だが、前掲書で中谷は、古来からの天才研究に連なる、その病跡学の核のまわりに、精神病患者の制作物の症状学的特徴への関心や、精神分析的な手法を用いた文学作品の解釈などやや異なった関心や方法が交錯してきたと述べている。そしていまや交錯するものは質も量もふえてきているのである。
第2部には、天才の創造性と――精神疾患から気質まで幅はあるが――その病理との関係を精神医学・心理学の文脈で論ずるという比較的オーソドックスな病跡学論文を集めた。が、それは「比較的」であって、例えばヴェルフリは病理と創造を扱うとともに精神病患者の制作物への関心の文脈にもある。
近年の動向として、神経発達症(発達障害)への関心の強まりがあるが、自閉スペクトラム症、あるいはもう少し広げて自閉症スペクトラムの病跡学を第3部に収めた。神経学的特性と表現とを単純に結びつけるだけでいいのかとか、統合失調気質(分裂気質)や中心気質との相違など深めるべき論点は多々あるが、病跡学の向かう道のひとつである。
第4部はサルトグラフィーに充てた。病理が創造性に影響を与えるばかりでなく、創造性が病理を緩和したり、いい影響を与えるという視点は昔からなかったわけではないが、より積極的に創造性と健康生成を論じていこうというのはもう一人の編者である斎藤環が打ち出したコンセプトである。また、身体疾患の病跡学に属する論考もここにある。
以上のように分類してみたものの、それはいささか強引だと思わざるを得ないほど、個々の論文の方向性は一様なものではないのだが、さらに第5部においてはラベルを貼りきれず、収拾のつかない様々な傾向をご覧いただく。「死」、「夢」、登場人物の病跡学、比較病跡学、精神分析的作品論、システム論……
パトグラフィーはどこまで来たのか、そしてさらにどこに向かうのか。
本書によって、パトグラフィーという領域があることを知らなかった方にその面白さを伝えたい。そして自分もこのような研究に参画したいという方をお招きしたい。
ようこそパトグラフィーの世界へ。
小林 聡幸